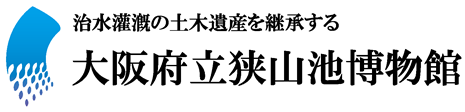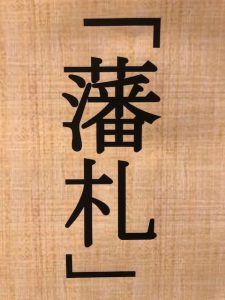令和2年度特別展「発掘された土木技術 大和川流域の開発と水制」の開催について
今年の秋の特別展では、「水制(すいせい)」を中心に、大和川流域の開発の歴史を紹介します。
水制とは、治水を目的とする河川構造物のひとつです。約1600年前の古墳時代には出現しており、その後、昭和の中頃まではよくみられた構造物でした。とくに、近世以降の古文書や絵図などに水制が記されており、日本各地の河川には様々な形の水制が設置され、川の流れを制御していました。
大阪平野の開発にあたって治水は重要な課題で、とくに大和川流域では古墳時代から様々な水制が存在しました。本展では、水制の歴史をたどりつつ、大和川流域の開発を紹介します。
会期 令和2年10月10日(土曜日)から12月6日(日曜日)まで
場所 狭山池博物館 1階特別展示室
入館料 無料
歴史セミナー
第1回 10月25日(日曜日)午後2時~午後3時30分
矢内一磨氏(堺市博物館学芸員)「大和川筋図巻を読み解く」
第2回 11月21日(土曜日)午後2時~午後3時30分
山田隆一(当館学芸員)「大和川流域の開発と水制」
各回共通
場所 狭山池博物館2階ホール
定員 60名(事前申込が必要。応募多数の場合は抽選を行います。)
参加費 無料
申込締切 令和2年10月10日(土曜日)必着
申込方法
・往復はがきをご利用の方
1通につき1名の申込となります。往信用裏面に①氏名、②住所、
③電話番号、④開催日(2回とも、あるいはどちらかの日付)をご記入
ください。返信用表面には、申込者の郵便番号、住所、氏名をご記入く
ださい。
宛先は「特別展歴史セミナー担当」あてとなります。
・Eメール
往復はがきと同様に、①~④の内容をご記入の上、下記アドレスへ
メールをお送りください。
oubo@sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp


(9月2日更新)
(9月20日更新)