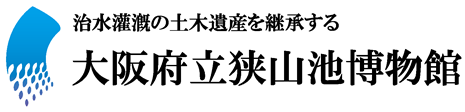下層東樋
 アーカイブ用-1024x809.jpg)
 アーカイブ用-809x1024.jpg)
 アーカイブ用-806x1024.jpg)
名称 下層東樋(かそうひがしひ)
時代 飛鳥時代~奈良時代
指定 重要文化財
概要
ため池に貯めた水を下流の農地等に向けて放水するための施設を「樋(ひ)」と呼ぶ。狭山池では飛鳥時代~昭和時代にかけて、3か所(東樋、中樋、西樋)に樋が設けられた。これらのうち、東樋では江戸時代の上層東樋と飛鳥~奈良時代の下層東樋が発掘された。
下層東樋は飛鳥時代につくられた樋である。コウヤマキの丸太をくりぬいた樋管を長さ約60mにわたってつないでいる。樋管本体とその蓋は、先端をソケット状に加工してつなぎあわせている。連結されたコウヤマキを年輪年代測定で調べたところ、西暦616年に伐採されたコウヤマキが使われていることが判明した。また、下層東樋は奈良時代に改修が行われ、一部が中心に新しい木材に交換されている。樋管の連結部分や蓋などに飛鳥時代と奈良時代の違いがよく見られる。